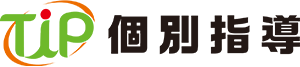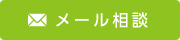中学受験を目指すご家庭では、春から夏にかけて学習量が一気に増える季節に入っています。
塾でもどんどん新しい単元に入り、模試や確認テストも頻度が上がってきます。
でもこの時期、保護者の方からよく聞くのが、こんな声です。
「塾には真面目に通っているのに、成績がいまひとつ…」
「授業は受けてるのに、家で問題を解けないんです」
「宿題もやってるのに、模試で点が取れない」
このような“見えにくい停滞感”の原因のひとつが、
**「集団授業の消化不良」**です。
授業についていけているように“見えて”、実はわかっていない
集団塾では、生徒たちのレベルに関係なく一律で授業が進みます。
-
ハイペースな進度
-
難易度の高い演習
-
1回の授業で大量のインプット
これらは受験対策としては非常に有効ですが、
“その場で理解したつもり”になってしまう子が出やすいのも事実です。
その結果──
-
先生が黒板で解説したときは「なるほど」と思う
-
でも、家で同じような問題を解こうとすると手が止まる
-
宿題は解答を見て写しただけになっている
こうした状態に心当たりはありませんか?
「消化しきれていないのに先に進む」リスク
中学受験のカリキュラムは非常に密度が濃く、
次から次へと新しい単元が押し寄せてきます。
その中で、1回理解した“つもり”で放置してしまう単元が増えていくと…
-
夏以降の応用問題でつまずく
-
過去問に入ってから“あれ、これ苦手だった”と気づく
-
そもそも理解の土台がないまま演習しても効果が出ない
という状態に陥りがちです。
実際、「夏から過去問を始めたのに点が全く取れない」と悩むご家庭の多くが、
春や初夏の基礎で“理解したつもり”だった単元が抜けているのです。
「授業についていけているか?」の確認ポイント
次のようなチェックをしてみてください。
-
宿題を一人で解けているか
-
単元の内容を親に説明できるか
-
テストで間違えた理由を本人が説明できるか
-
同じような問題を何日か後に解いてもできるか
これらができないようであれば、
授業の内容が完全に定着していないサインです。
「わかるようにする」のは誰か?
集団授業は、基本的に「わかるように教える」場ではありますが、
「その子がわかるまで寄り添う」場ではありません。
一方通行の説明はあっても、
一人ひとりのつまずきを拾い、確認し、修正する時間は限られているのが現実です。
だからこそ、保護者の方が
「今の塾、ちゃんと本人に合っているのかな?」
「授業をこなすだけになっていないかな?」
という視点を持って見守ることが、とても大切です。
本当に大事なのは「自分の力で解ける」こと
塾での授業を聞く
→ 先生の解説を理解する
→ 解説なしでも解けるようになる
→ 時間が経っても覚えている
→ 応用にも対応できる
このプロセスが、しっかり身についているかどうか。
ここを丁寧に見直すことが、夏からの成績の伸びに直結します。
集団授業は効果的な面も多いですが、
それだけで十分かどうかは、お子さんの様子を見て判断が必要です。
もし、「理解できていないかも?」と感じたなら、
今が立ち止まるタイミングかもしれません。