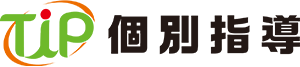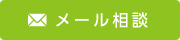「わかりやすい」って、そんなに大事?
今日は、以前にも書いたテーマのリライトです。
でも、今年改めて取り上げたいと思いました。
なぜなら、「わかりやすい授業」というキーワードが、ますます当たり前になってきているからです。
TIP個別指導でももちろん、生徒にとってわかりやすい説明を心がけています。
実際、「先生の説明わかりやすい!」という声もよくいただきます。
生徒が「わからない」から塾に来るのですから、それに応えるのは当然のこと。
ただ最近、この「わかりやすさ」が過剰になっていると感じる場面が増えています。
「わかりやすい」の落とし穴
授業が「わかりやすい」と、生徒はスッキリします。
「なるほど、そういうことだったのか!」と感じて、やる気が出る。
でも、そればかりだと、実は危ないんです。
「わかりやすい授業」を受けることに慣れすぎると、
生徒は自分で考える力を使わなくなっていきます。
“考えなくても教えてくれる”
“わからないところは待っていれば解説がくる”
この状態に慣れてしまうと、「思考の筋力」はどんどん落ちていきます。
映像授業も、AI教材も…わかりやすい。でも…
最近では、AIによるタブレット学習も増えています。
問題に答えると即座に解説が返ってきて、正誤もすぐわかる。
非常に「効率的」で「わかりやすい」仕組みです。
しかし、ここにも課題があります。
与えられた問題に答え、正解すれば満足してしまう。
でも、それが「わかった」ことと「できる」ことは別物です。
特に初見の応用問題に出会ったとき、
ヒントがなければ手が止まってしまう──そんなケースがよく見られます。
「思考する時間」があまりにも短くなっているのです。
試行錯誤を通じてしか、実力は育たない
生徒が成長する場面って、実は「わかりにくい」と感じたときだったりします。
うまく説明されなくて、「え?どういうこと?」と悩む。
その時、頭の中で考えようとしますよね。
その思考こそが、実力につながるのです。
ですから、私は授業の中であえて、解説の“階段”を飛ばして話すことがあります。
すると、生徒の表情が変わります。
「今の、どういう意味だ?」と考え出す。
そして、その“飛ばされた一段”を自力で埋められるようになってくると、
その子は本当に伸びていきます。
もちろん、その飛ばす段差が大きすぎると混乱します。
だから、「どの段を、どれくらい飛ばすか」は、生徒によって調整します。
それが講師の工夫であり、経験の見せどころです。
「わかりにくさ」にも価値がある
最近は世の中全体が「親切」になりすぎているようにも感じます。
すぐに答えがわかる。
すぐに動画で説明してくれる。
わかりやすさは、たしかに大切です。
でも、**「わかりにくさの中から、自分なりに答えを見つけていく力」**を、今の生徒たちにはもっと育ててほしいとも思っています。
「先生、ここちょっと飛びましたよね?」
「自分なりに考えてみたんですけど、こういうことですか?」
そんな会話ができるようになったとき、
生徒は大きく変わっていきます。
最後に
「わかりやすい授業」は、学習の入口としてはとても有効です。
ただ、それだけで完結してしまっては、本当の力は身につきません。
TIP個別指導では、ただ“教える”のではなく、
“考える場面を残す”ことを大切にしています。
生徒が自力で階段をのぼっていく、そのサポートをする。
そんな授業を、これからも目指していきたいと思います。